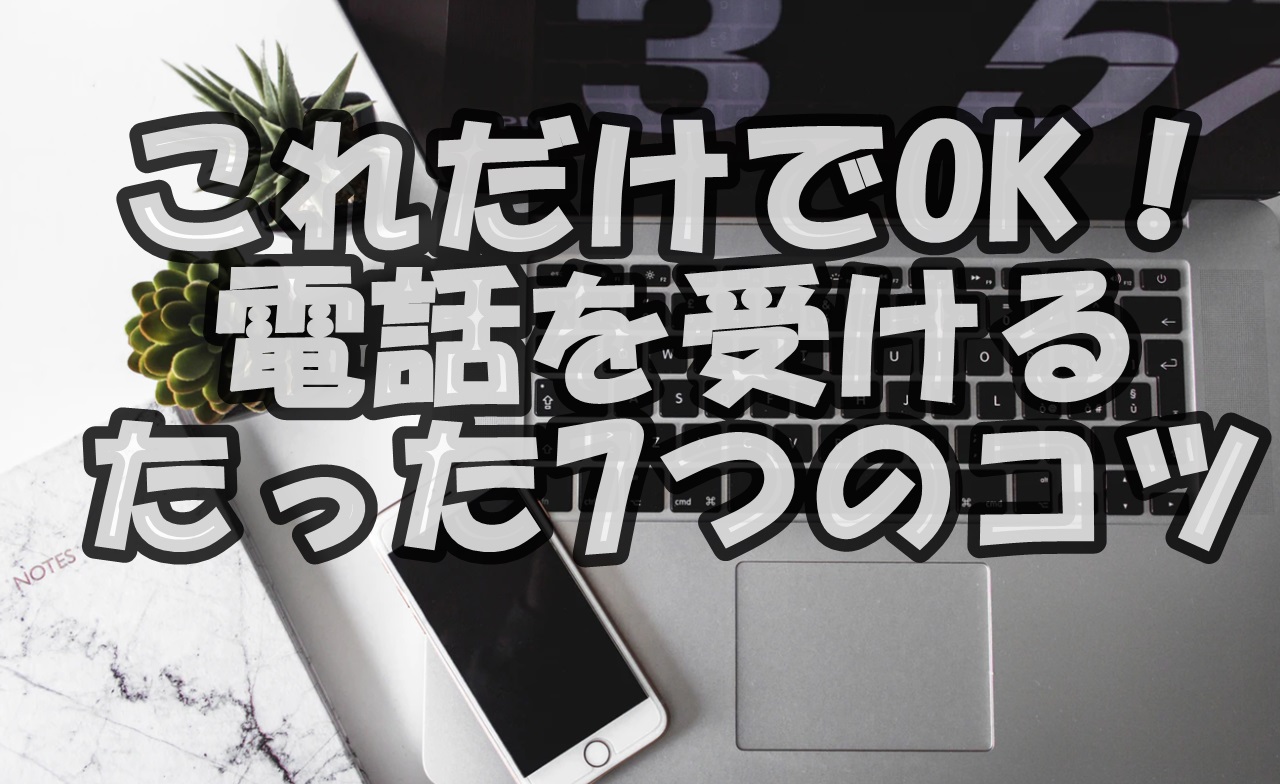オフィスの電話が鳴ると「ドキッ」としませんか?
現代はメールでのやりとりが多く、直接的に話をすることが少なくなってきました。
通話に慣れていない人が増えているのです。
なので、いざ会社でとらないといけない場面になると緊張してしまうのではないでしょうか。
着信音が鳴ったとき
「できればとりたくないな」
「誰かがとってくれ~」
そんな風に思ってしまうあなたに、この記事では電話を受ける際に押さえておくべきマナーや注意点を紹介します。
応対がちょっと苦手だなと感じている方に、ぜひ読んでいただければと思います。
受電することが大切なのはなぜ?


ゆうこさん、オレ電話がかかってくるとどうしてもビビってしまうんです。
なんとかなりませんかね・・・。

誰でも最初は緊張して当たり前よ。
じゃあ今日は受けるときのコツについて話すわね。

お願いします!
ビジネスシーンにおいて電話応対は絶対に必要なスキルです。
でも、誰がどんな用件でかけてきているかがわからないので不安ですよね。
また「すぐに言葉を返さなければいけない」と思うとつい緊張してしまうものです。
新入社員研修では必ず電話対応の研修を行います。
ビジネスにおいて電話というツールは必需品で、この対応ができないと仕事に支障をきたすからです。
何回も何回もロールプレイを繰り返してから、現場での実践に入るくらい重要です。
なぜなら相手にとっては、対応した人が会社の代表者になるわけですから。
4月の新入社員のうちは多少ミスしても許されます。
でも3ヶ月経ってもミスしてると、恥ずかしい思いをするでしょう。
後輩が入ってきて「あの人、電話もろくに取れないんだな」なんて思われたら残念ですよね。
失敗しても最初のうちにどんどん積極的にとって、たくさん応対をしてすぐに慣れることが怖くなくなる一番の近道なのです。
気をつけること7つ!

それではさっそく注意点を見ていきましょう。
1.3コール以内に出る
着信音が鳴ったらすぐに出ましょう。
一般的にはコールは3回以内にとるのがマナーと言われています。
これは、かけてきている相手を待たせないためです。
メールなどのツールが増えている中で、わざわざ通話を希望しているということは、
相手が急いでいたり、内容が見落とされたくない重要なものだったりする可能性が高いのです。
「すぐに出てくれた」というだけで、相手は安心できます。
安心して話をしてもらえた方が、こちらも気持ちが楽になりますよね。
もし3コール以上になってしまった場合は、「お待たせいたしました」と添えましょう。
2.しっかりと名乗り、相手がだれか確認する
ビジネスでは受話器をとったら「もしもし」ではなく「はい」と返事をします。
そして、まずこちらから名乗るのがマナーです。
会社によって名乗り方のルールを設けている場合がありますが、基本的には社名と対応している自分の名前を伝えます。
こちらが言い慣れるとつい早口になってしまいますが、相手が聞き取れるよう、ゆっくりとハッキリ名乗りましょう。
そうすることによって、自分自身も気持ちを落ち着かせることができますよ。
電話をかけてきた相手を確認し、聞き間違いのないように復唱します。
直接面識がない場合でも、挨拶をかわしましょう。
社外の方であれば「お世話になっております」、社内の方であれば「お疲れさまです」となります。
その後の会話へとスムーズにつなげられますよ。
3.適切な相槌をうつ
話している間は会話に集中しましょう。
お互いの顔が見えないので、かけている側は常に「きちんと聞いてくれているかな」と気にかけています。
こちらがメモに気を取られたりして無言の間があくと、相手は不安になってしまいます。
相手の話の区切りがつくタイミングで「はい」「かしこまりました」などの相槌をうちましょう。

こちらの言葉が相手の言葉に重ならないように注意よ。
相手が言い終わらないうちに言葉をかぶせてしまうと、相手は話をさえぎられたような気持ちになるので注意してね。

なるほど!
いったん言葉をとめて、相手の言葉を待つのがコツですね。
4.用件を復唱する
自分あてでも、他の社員あての取次でも、用件を正確に聞き取ることが大切です。
「○○ということですね」と復唱することで思い違いを防ぐことができます。
それだけでなく、相手にとっては「きちんと受け止めてくれた」という気持ちになり、印象がぐっと良くなります。
この復唱をしただけで「そうそう、そうなんだよ」と、その瞬間からあなたのことを信用して話してくれることもあります。
逆に復唱がないと、言っていることが伝わっているのかどうかがはっきりせず、もやもやと不安になってしまいますよね。
たとえ話の内容自体が分からなかったとしても、「どういうことで電話をかけてきたのか」をつかむだけで大丈夫です。
応対に慣れてきたら「一言でいうとどういうことだろう?」と考えながら話をよく聞くといいですよ。
ぜひ試してみてください。
5.保留にするとき
保留にする場合にも注意することがあります。
即答できず確認が必要な場合は「確認いたしますので少々お待ちいただけますか?」と相手の承諾を得て引き伸ばします。
時間は長くても1分以内としましょう。
調べているこちらはあっという間ですが、待っている側は1分間でもとても長く感じるのです。
戻ったら解除して「お待たせいたしました」と伝えてから会話を再開しましょう。
6.社員の個人情報を教えないようにする
個人情報の取り扱いには十分な注意が必要です。
取次で担当者が不在の場合、相手から「直接連絡してみるので携帯の電話番号を教えてもらえますか?」などと求められることがあるかもしれません。
あらかじめ「社用の携帯番号であれば先方に伝えて良い」という社内ルールがあれば、それに従いましょう。
しかし、とくに定められていない場合は勝手に言わない方がベターです。
「担当者より折り返します」で通しましょう。
社員の在籍情報や異動情報なども決してむやみに知らせないように気をつけましょう。
7.先方が切るまで待つ
電話のマナーは、基本的に「かけた方が先に切る」ことになっています。
先方からかかってきたのであれば、会話が終了したらすぐに切らずに、相手が受話器を置くのを待ちましょう。
もしかしたら伝え忘れていた用件があるかもしれません。
話が終わったらからといってすぐに切ってしまうと、切られた相手は良い思いはしないものです。
最後の最後まで気を抜かずに、気持ちの良いやりとりで終われるように心がけましょう。
気をつけること まとめ
慣れていないうちは、電話機がそばにあるだけでドキドキするものです。
「鳴ったらどうしよう、怖いな」と思ってしまいますよね。
しかし、一件一件に対して自分なりに丁寧に対応していくことで、自分の「型」ができあがります。
「型」を身につけると対応が苦ではなくなり、面白いと思えるようになりますよ。
今回紹介した内容はマナーや注意点ではありますが、同時に、自分自身が安心して対応するための効果的な方法でもあります。
職場で電話を受けるときは
・遅くとも3コール以内に出る
・ゆっくりめにはっきりと名乗り、かけてきた相手を確認する
・適切なタイミングで相槌をうつ
・用件を復唱する
・即答できず確認が必要なときは保留にする
・社員の個人情報を告げないようにする
・相手が切るまで切らない
これらのことを押さえていれば、電話対応も怖くないですね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
それではまた次回!